7年前,我读大学2年级时首次选了陈文权教授的课 soetanto method 13
- 2012/07/10 08:40

7年前,我读大学2年级时首次选了陈文权教授的课。
栄琦(ロン・チ GIGI)
日本早稻田大学国际教养系毕业生
课堂上得知陈教授克服了重重困难,取得了现在的成就和地位。他那种在任何情况下都『永不放弃』的精神,给我之后的人生道路以巨大影响。另外,陈教授在为人处事时,即使不被理解,也能做到『给予,给予,再给予』(不求任何回报)。如果可能的话,我希望能象陈教授那样坚强地生活。虽然是大2时上的课,但是在陈教授课堂上所学内容,至今依然是我为人处事的规范。
毕业后我曾当私塾老师。当时,我将从陈教授课堂上学到的方法,运用到我的教室。『你自己到底想做什么?』『自己独立思考是否重要?』『你自己到底想成为怎样的人?』等等,我向或者学生提问,或者在上课前后与学生的轻松谈话中有意提到“目标”等话题,让他们发言,整理思路。目标,方法等明确的话,学习热情就会提升。这也是上陈教授的课学到的方法。学生评价我的课很严格,多亏“陈文权教学法”,学生一直保持高涨的学习热情。至今我和当时教过的学生还保持联系,甚至几年后他们还对我所教的内容依然记忆犹新。能给他们这种积极影响,也许可以归功于如何激发学习热情的“陈文权教学法”的科学性。
我将来想从事企业人才教育,所以当了一年的私塾老师后便去美国留学,攻读工商管理硕士。毕业后在美国的一家大型通信机器企业就职。因为父母都在日本工作,我又回到日本。
到目前为止,我之所以能比较顺利的实现自己的愿望,与我大二时选修陈文权教授『MOTIVATION&EDUCATION』(『学习热情与教育』),受到陈教授的重大影响分不开。
我的最终目标是掌握“陈文权教学法”,作为教育工作者,一步一步接近向陈教授靠拢。即使过去好几年,还能给他人的人生带来积极影响,这不正是自己人生价值的体现吗?即使前方道路艰难险阻,只要不放弃,就有希望。至今我对大学时代能接受陈文权教授的指导心存万分感激。

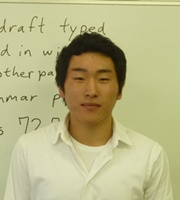

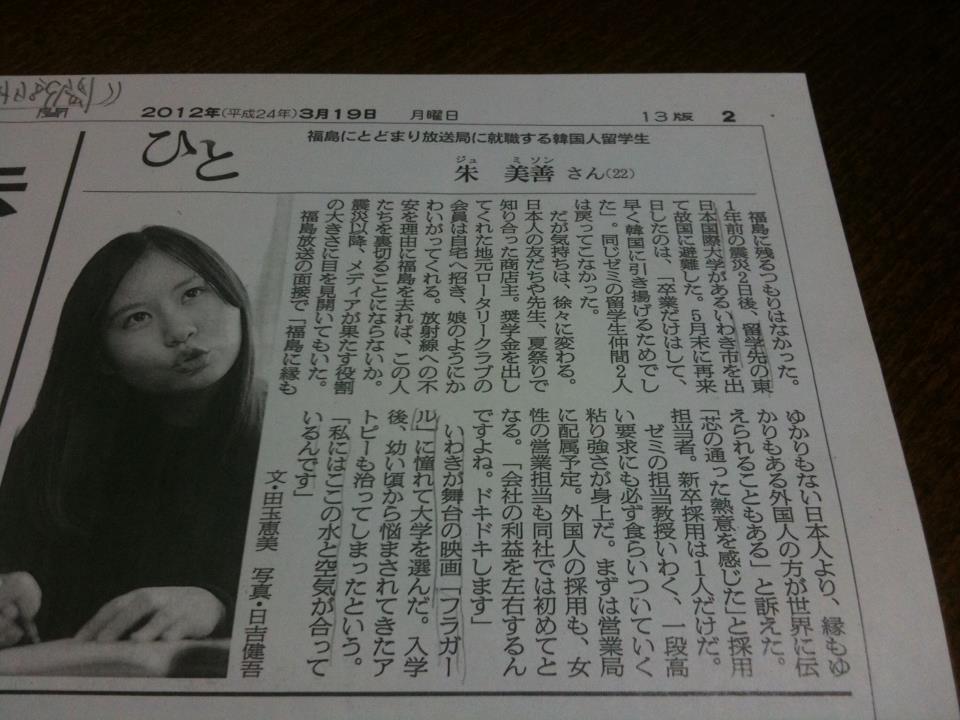





.jpg)

