次世代を担う幹部候補としての採用 未来の「ふつう」を次々と。人口減少社会×ITで全9事業展開中のベンチャー企業
- 2020/02/15 18:48
 業務内容】
業務内容】弊社の次世代を担う幹部候補としての採用です。
これまでのご経験や適性を踏まえ配属先を決定いたします。
弊社は「人口減少社会への価値貢献」をミッションとする創業5年目のスタートアップですが、現在合計9事業を多方面に展開中で、全国7拠点、従業員230名が在籍する急成長フェーズにあります。
今後は既存事業の成長はもちろんのこと、2020年までには複数の新規事業をリリースしていく予定です。
その実現に向けて、プロダクト開発・事業企画・セールス・コーポレート、あらゆる機能の拡充が欠かせない状況です。
今までの大企業/ベンチャーでのご経験を活かし、これからはもっと自分の力で会社や事業にインパクトを与えていきたいと考えている方に、弊社でしか得られない”実行力”を身に付け、理想のキャリアを実現していただきたいと考えています。
※全国にて募集
<配属先候補> ※その他にも配属可能性がございます。
・既存事業および新規事業におけるセールスマネージャー候補(営業活動の実施およびセールス領域全般の企画~実行~管理までの一連を担って頂きます)
・「人口減少社会において必要とされるインターネット事業の創造」の企業理念に基づいた新規事業の企画~実行~管理までの一連を担う事業責任者候補
・既存事業および新規事業におけるマーケティング領域のマネージャー候補(SEO/SEM等のデジタルマーケティングおよびDM施策/専門誌への出稿等のリアル・マーケティング)
・経営企画、事業企画、人事などバックオフィススペシャリスト等
【オープンポジション/次世代幹部候補】
他社にはない”激動”求める方、入社後1年でCXO/事業責任者を目指しませんか?
【必須スキル・経験】
・大卒業以上
・目標に向けPDCAを回した経験
・他部署を巻き込んで仕事をした経験
・ビジネスを通じて社会貢献をしたい方
【歓迎スキル・経験】
・IT企業、メガベンチャー出身
・0→1の経験
【求める人物像】
・当社の事業やビジネスに興味関心がある方
・成長分野での自己成長、自己実現を叶えたい方
・自分の仕事の価値や存在意義を実感したい方
・0→1を生み出したい方
【勤務時間】
10:00~19:00(21:00完全退社)
【募集拠点】
拠点(既定)
東京都渋谷区
【勤務地】
全国転勤の可能性あり
【想定給与】
年俸制:420万円~840万円
※試用期間:3ヵ月
- 2020年4月より賞与制に移行
※年収の14分の1が月給、残りの14分の2が賞与のベースとなり、半期毎の評価はこの賞与に反映されます。
【休日・休暇】
【年間休日125日以上】
・完全週休2日制(土・日曜日)
・祝日
・有給休暇
・夏季休暇 (3日)
・GW休暇
・年末年始休暇
・9連休制度(土日を含む計9日)
・慶弔休暇
・産前産後休暇・育児休暇
・アニバーサリー休暇
【待遇・福利厚生】
多様な国籍・カルチャー・バックグラウンドを持つ人材が互いに尊重し、一人ひとりの能力を最大限に発揮することで、より活発でフラットな組織になると考えています。個人個人がいきいきと活躍することで、より事業や会社の成長を促進していけると考えています。
- 社会保険完備
- 交通費支給(上限あり)
- 21時完全退社
- 家事代行利用補助制度
- 病児保育補助制度
- 昼活(社員の健康増進とコミュニケーションの促進を目的に健康的な昼食を無料で提供)
- 夜活(社内外のコミュニケーション促進を目的にお酒や軽食を無料で提供)
- グロービスeMBA受講制度
- エンジニア書籍購入制度
- 英語レッスン(毎週1回30分間、ネイティブ講師と1 on 1で実施)
- ベンチャープログラム(入社半年以上の社員なら誰でも新規事業の立案が可能)
- 部活動サポート
- チーム達成会、食事会費用負担
- 出勤時間前倒し制度(始業時間を最大2時間前倒しすることが可能)
- 9連休制度(年度内に土日を含む9連休を自由に取得可能)
- 長期在籍&貢献報奨金(勤続年数に応じて報奨金を支給)
- 出産後の早期復帰を支援(女性正社員が出産後早期復帰する場合、保育園入園までのベビーシッター費用を100%補助)
- 様々なバックグラウンドを持つ社員が集まる圧倒的成長環境
- on・offのスイッチが切り替えやすい空間づくり
・戦略的仮眠室(従業員の生産性向上を目的に、短時間の睡眠を推進)
・マインドフルネス(外部講師をお招きして、集中力アップやストレス軽減に効果があるヨガやマインドフルネスを実施)
・スタンディングミーティング(社内会議は原則スタンディングで実施し、無駄な会議を削減)
・リフレッシュエリア(最上階である9階フロアは、社員が自由に休憩できる空間)
給与 年俸制:420万円~840万円
※試用期間:3ヵ月
- 2020年4月より賞与制に移行
賞与:年2回(6月/12月)
※年収の14分の1が月給、残りの14分の2が賞与のベースとなり、半期毎の評価はこの賞与に反映されます。
雇用形態 正社員
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
問い合わせ
グローバルコミュニティー編集部 編集長
学生通訳ボランティアガイド連絡会 事務局
国際紅白歌合戦実行委員会代表
宮崎計実
160-0022 東京都新宿区新宿6-7-1 Elpuriment 新宿 502号
globalcommunity21@gmail.com
070-5653-1493
ーーーーーーーーーーーーーーー
グローバルコミュニテイーが目指すもの
http://www.yokosojapan.net/article.php/globalcommunity2013_editor_ja
観光庁後援第9回国際紅白歌合戦、2019年10月27日(東京オリンピックセンター
)開催、協力団体・参加者・ボランテイアの皆さま、誠にありがとうござました。
2020年は9月27日『世界観光の日』に開催いたします。
http://www.irws.org/
やる気があれば誰でも出来る通訳ボランティアガイド
http://www.yokosojapan.net/article.php/guideinternational_ja
GLOBALCOMMUNITY NEWSLETTER 2020.1
https://www.yokosojapan.net/article.php/20191231newsletter2020_editor_ja

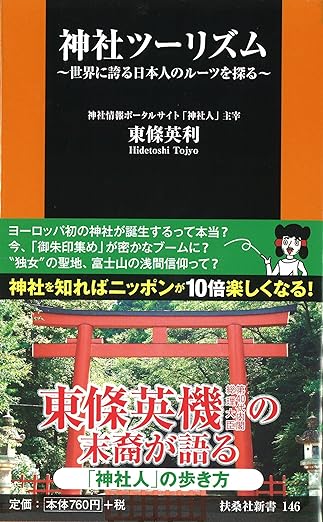

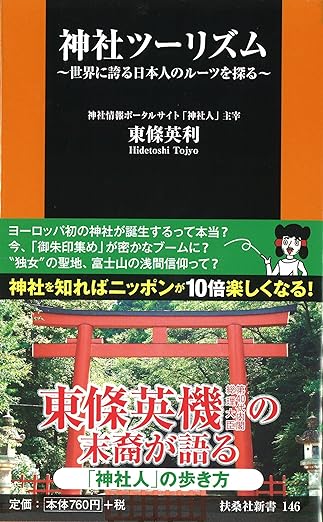
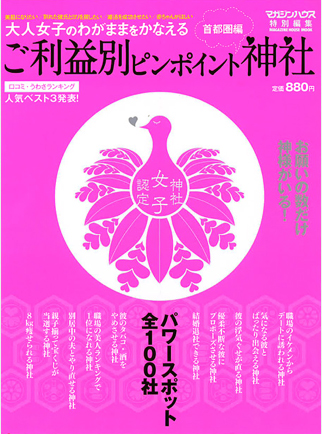
.jpg)